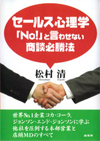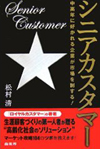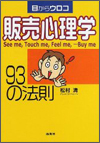金持ちも貧乏な人も、得な買物をしたい。金持ちはディスカウントを楽しむし、貧乏な人はディスカウントが必要なのである。そのため小売店は「ハイ・ロー戦略」やエブリデーロープライス戦略を取る。ウォルマートが行ったエブリデーロープライス戦略には、ローコストオペレーションが出来るシステムや企業体質がなければならない。それがないまま単に価格だけを下げた小売業はほとんどが失敗し、結果的に収益力を著しく下げてしまった。

主要商品を定期的に一定期間ディスカウント価格で販売し、それ以外のときはプロパー価格で販売するというやり方である。ディスカウント対象商品をチラシに載せると、清涼飲料水のような商品の売れ行きがよくなる。フレグランスのように、ディスカウントで買ったからといって消費量が増えるわけでない商品は余り売れない。使用頻度、購入頻度の低い商品はチラシに載せても、お客の目に留まらない確率が高いが、消費量の多い清涼飲料水等は目に留まるからだ。これを利用したのがハイ・ロー戦略である。この戦略には、次のような効果がある。
価格に敏感なお客をターゲットにする店では、エブリデーロープライス戦略が有効である。絶えず低価格で販売されているので、ディスカウント販売をしない。この価格戦略はウォルマートが採用して一躍有名になったものである。この戦略の優位点は次の通りである。


価格は300円とか1000円のように、「0」で終わる付け方をしてはいけない。「8」とか「9」にすると、お客の印象に大きな違いが出るからだ。これら端数にはどんな効果があるのか? 「0」以外の端数の方が安く感じる。人は10、20、30という「0」が最後につく数字を1つの区切りや単位にしている。だから19歳と20歳、29歳と30歳では、たった1歳の違いだが受け取り方に大きな違いがある。1万円と9980円はわずか20円の違いだが、人々に与える印象は違う。最後のケタが「0」以外の端数で終わると「安い」と感じ、「0」で終わると「高い」と感じる傾向があるからだ。最終ケタが8や9の端数と、0とでは印象に違いがあるが、8円と9円、4円と5円の端数同士ではあまり大きな差はない。もう少し端数の効果について述べよう。

 コンピュータ関連の商材を販売しているあるチェーン店は、「9」「7」「1」の3つの端数に限定するという面白い端数価格政策を実施している。チラシ対象商品の中でも優先順位は違うので、最も力を入れて販売したい商品(例:ヒューレットパッカードのコンピュータ1599ドル91セント)には端数を「1」にし、2番目に力を入れたい商品(例:エプソンのスキャナー199ドル97セント)は端数を「7」、そして3番目が残りの商品(例:デスクトップのキーボード59ドル99セント)は端数を「9」にしている。それは、主役商品のコンピュータを買うと決めた後は、関連品のスキャナーやキーボード等に対する価格志向が薄れているので、出来るだけ利益を取ろうとしているのである。
コンピュータ関連の商材を販売しているあるチェーン店は、「9」「7」「1」の3つの端数に限定するという面白い端数価格政策を実施している。チラシ対象商品の中でも優先順位は違うので、最も力を入れて販売したい商品(例:ヒューレットパッカードのコンピュータ1599ドル91セント)には端数を「1」にし、2番目に力を入れたい商品(例:エプソンのスキャナー199ドル97セント)は端数を「7」、そして3番目が残りの商品(例:デスクトップのキーボード59ドル99セント)は端数を「9」にしている。それは、主役商品のコンピュータを買うと決めた後は、関連品のスキャナーやキーボード等に対する価格志向が薄れているので、出来るだけ利益を取ろうとしているのである。最近良く目にするのが、「3個目フリー(無料)」「2個目50%引き」などの価格設定だ。3個目フリーと言うことは1個辺り33%引きと同じだ。2個目50%引きは1個25%引きと同じだ。どうしてこのような表現をするのか?
プロフィール

Excell-Kドラッグストア研究会(http://www.drugstore-kenkyukai.co.jp/)、Excell-K薬剤師セミナー、及びExcell-Kコンサルティンググループを率いる流通コンサルティング会社Excell-K(株)ドムス・インターナショナルの代表者。小売業、卸店、メーカーに対するコンサルテーションをはじめ、講演、執筆、流通視察セミナーのコーディネーターとして活躍。特にドラッグストア開発、ロイヤルカスタマー作り、シニアマーケティングのための実務と理論に精通し、指導と研究では第一人者。年間半年を米国で生活し、消費者の目・プロの目を通して最新且つ正確な情報を提供しながら、国内外における視察・セミナー・講演を精力的にこなす。
日本コカ・コーラ(株)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)を経て独立('90)。慶応義塾大学卒(法学)、ミズリ―バレーカレッジ卒(経済)、サンタクララ大学院卒(MBA)。東京都出身。

■全米No.1のドラッグストア ウォルグリーン