中国毒ギョウザ、汚染米…など食品に関する事件が相次いでいる。消費者の食の安心・安全意識が過剰なほどに高まる一方、“真犯人”不明のまま報道が先行し、あらぬ風評被害に苦しむ事業者もいる。ナゼこの種の不祥事が起こるたびにメディアは“危険報道”に走るのか。メディア側からその構造を分析した「誤解だらけの危ない話」(エネルギーフォーラム)の著者で毎日新聞編集委員の小島正美氏に聞いた。
基本的には少しでも危険があればそれを報じるのはメディアとして当然の役割です。その上で、いわゆる「危険報道」が発生するメカニズムとして、そちらの方が市民のニーズがあるからということが考えられます。そこへプラスして、担当記者が科学についての知識があまりない場合、どうしても危険性を強調する専門家のコメントを鵜呑みして書いてしまうことがあるということではないでしょうか。

例えばそれが政治家のコメントであったり、公共事業などの問題なら、記者もいろいろ突っ込んで取材すると思います。ところが、食品添加物となると「危険だ」で終わってしまう。書物や専門家などの話から固定概念ができ、思考が停止してしまっている。もちろんこれは憂うべきことであり情けないことです。ただ、こうした点について、ハッキリといえることがあります。それは、主導権は、あくまで情報を出す企業側にあるということです。メディアは当然ですが、なにかがあって初めて動きます。仮に企業を介さず、ネガティブなことを報じられてしまった場合でも、まだ企業に主導権はあります。そのことをしっかりと認識しておく必要はあると思います。
あの件はひとつの教訓といえるのではないでしょうか。というのも、あの時も企業にはやはり主導権はあった。にもかかわらず、国の不正確な発表と不十分な報道を打ち消す発表を十分にしなかった。聞いたところでは、記者クラブなどへのリリースをしたということですが、では、例えばしかるべき部署へリリースしたのか。新聞社でいえば、文化部や社会部、経済部、運動部などいろんな部署がある。適切な部署へ送らなければ、「送った」といってもうまく機能するとは限らない。なにより、しっかり報じてくれなかったとしても報道に誤解があるなら、何度でもアプローチして、発信するのです。報道の誤解を解消するに値するしっかりとしたエビデンス等があるならば、自信を持って反論すべきです。

ひとつの対策としていえるのは、メディアに対し、積極的にセミナーを開催するということがあると思います。先に言ったように記者の場合、いろいろな部署を経験するのが普通ですからどうしても専門的知識が乏しくなりがちです。それが原因で、ミスリード的な報道が起こるとすれば、それは記者自身が勉強しなければいけないのは当然ですが、企業側が事前にそのリスクを減らしたり、誤った固定概念を修正する方策として勉強会を開催するのは有効な手段のひとつといえるでしょう。2、3ヶ月に一回でも勉強会も兼ねたメディアセミナーを実施すればいいと思います。薬品メーカーは昔から行っていますよね。規模の小さい健康食品メーカーで予算的に難しいのであれば、いくつかの企業で合同開催してもいいと思います。
それから私の感覚では、健康美容関連の業界は、悪いことを起こした企業があった場合、救いの手を差し伸べるのではなく、そことの比較で「ウチは違う」というスタンスで、さらに蹴落とし、自分たちの売り上げアップを考える傾向があるような気がします。いろいろな問題があるのでしょうが、そうではなく、ネガティブ報道は業界の沈没にもつながるという意識を持って、時には団結して、反論するような動きも必要なのではないでしょうか。
難しい部分も多いと思いますが、業界として常に問題をチェックできるような仕組みなりを作っておくことは大切だと思います。そのためには、しっかりとしたエビデンスなり、例えば動物実験でもどんな類のものなのか、といったことを各企業が正確に伝えられるように材料をキチンと揃えておく必要があるでしょう。

当たり前のこととして、情報を鵜呑みにする前に、冷静になってまずは直接企業に問い合わせることです。どういうデータがあるのか、そのデータが動物実験で行われたものならどんな動物実験なのか。原料なならその原産地はどこなのか。とにかく納得のいくまで質問することです。教えてくれない会社なら信用などできるはずがありません。商品ラベルや広告などから得られる情報についていえば、あまり大げさに書かれているものは当然注意する必要があります。エビデンスについては、科学雑誌や医学雑誌に出たものである、ということがひとつの目安になります。あとは学会発表されているのか、論文になっているのかというということもしっかり確認した方がいいとでしょう。そうしたことを踏まえ、いえることは「情報に気軽にアクセスができるかどうか」が、その商品や会社が怪しいかどうかを見極めるポイントになるということです。
先ほど申したように危険報道へのニーズが多い一方、安全については確かに“情報屋”としての観点から考えても「売れる」といえるものではありません。従って、報じていないことはないにしても目立たない場合が多いかもしれません。それに加え、危険についての情報の驚くべき伝播スピードに比べ、安全情報は伝える活動を行っている人たちのネットワークがなかったりするなどで末端まで伝えるハブ機能(熱意にあふれた核となる人)がない。それが最大の弱点といえるでしょう。
プロフィール
1951年 愛知県犬山市生まれ。愛知県立大学卒業後毎日新聞社入社。長野支局、松本支局を経て1987年より東京本社・生活家庭部配属。1995年に千葉支局次長を務め1997年より生活家庭部編集委員として、主に環境や健康、食の問題を担当。東京理科大学非常勤講師も務める。著書は最新刊「誤解だらけの危ない話」、「動物たちはいま」「海と魚たちの警告」
「化学物質の逆襲」「人体汚染のすべてが分かる本」など多数。
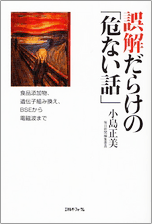
さまざまな食品関連事件が相次ぎ、食の安心・安全に対する消費者の意識はかつてないほど高まっている。裏を返せば、消費者の間に「不安」がまん延している。「食品添加物」「遺伝子組み換え作物」「食品の残留農薬」…実際には健康を害するリスクがないはずのささいなリスクに対し、消費者はなぜか過剰なまでに防御反応を示す。本書ではその不可解な原因の「正体」を現場を取材する記者の目から解析している。健康番組の功罪、記者の問題点、不安情報が乱発される背景…など立場上いいにくいところにまで踏み込み、危険報道発生のメカニズムを解説。さらにその対処法などを提言している。

URL
http://www.mainichi.co.jp/home.html
毎日新聞社
■創刊:1872年(明治5年)2月21日
■資本金:41億5000万円
■約3,200人
■本支社:東京本社、大阪本社、西部本社、中部本社、北海道支社
■通信網:総・支局101、通信部・駐在265、海外機関26
■印刷拠点:15工場